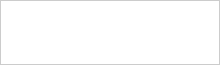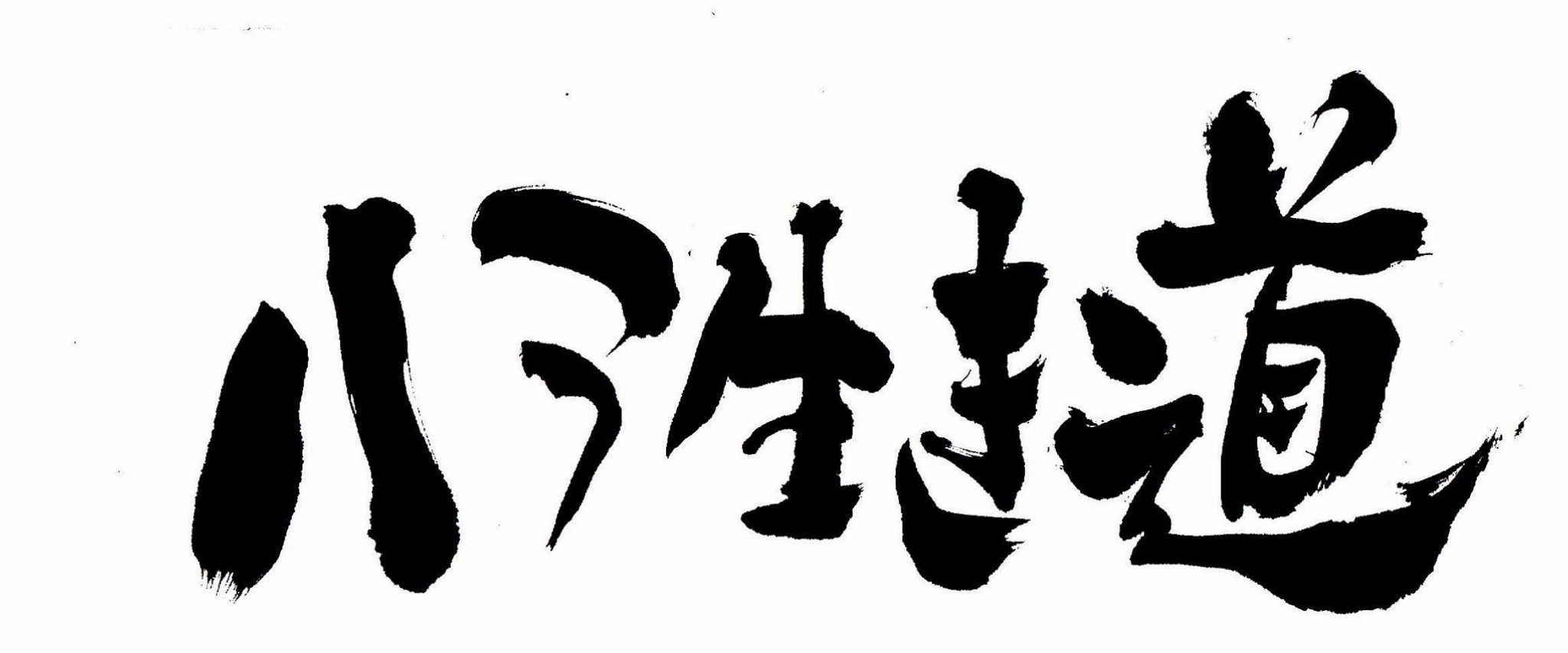多様で多角的な視点を持つこと。
それが研究には必要だ。
「合気」の研究をはじめたのは、名古屋大学の合気道部に入部した2003年頃から。
当時は「合気道」が上達したいだけだった。
なぜ、それほどまでに合気道が上達したかったのか、その理由は分からない。
ただただ合気道に惹かれ、合気道の稽古ばかりしていた。
どうしても上達したかったので情報を求め本屋や図書館などで合気道の本を読み漁った。
西郷派大東流の「合気完成90日」なんかも読んだ。
合気道ならなんでもよくて富木流の本も読んでいた。
そんななかで「透明な力」に偶然にも出会った。
そこからは「合気道の上達」というよりは「合気の研究」に没頭していった。
学生のころから東京・大阪と出稽古に出かけたり、ちかくの大学の合気道部に参加したりして研究を続けた。
そんなこんなで現状がコチラ。
まったく達人なんてものには程遠く、恥ずかしいばかりの映像だが、15年前に比べれば少しは上達したと言えるだろう。
さてそんな研究が、このところまたカオスになっている。
実用的な「和の礼儀作法」がある程度完成したところで、個人的マニアック研究に火が付いた感じだ。
現状、知識を仕入れすぎてカオスになっているので、自身のアタマをまとめるためにも記しておきたいと思う。
目次
合気道 極意の秘密
言うまでもなく吉丸慶雪さんの著書。
この本における「極意の秘密」とは宮本武蔵のいう「うつらかす」技法だと言う。
こちらが強い力を出し、相手がそれに反応したとき、それを滑らかに「弱い力」に転換する。
すると、相手もつい力を抜いてしまうため、その隙をついて再度「強い力」を出すことで、相手に勝つという。
「伸筋の力」というワードが多用される。
吉丸さんが太極拳を学んでいたためか中国拳法の「勁」の概念で合気を説明しようとしたことが見て取れる。
できる!使える!合気上げ
吉丸さんのお弟子さん有満さんの本。
吉丸さんの伸筋理論を継承しながら、さらに発展させた一般向けの本。
特段、新しいことはなかったが「地球に力を流す」というコンセプトは、ぼくの研究と一致していると思った。
新次元武術 気空術【合気の秘密】
尊敬する畑村先生のDVD。
先生ご自身の演武が少なく初心者向けの説明に留まると感じた。
「愛」などは極意と思われるが、DVDからはどうしても感じ取りにくい。
合気完結への旅 透明な力は外力だった
保江さんの考えは元々好きで本もよく読んでいた。
しかし「宇宙船の司令官」あたりからおかしくなったと思い、本を読むのをやめていた。
しかし今回なぜか保江さんの本にチャレンジしたくなり購入。
これが当たりだった。
保江さんの「合気修得」までの道のりが事細かに記載されていて、非常に参考になる。
ただ保江さんが佐川先生の合気を「修得」したのかどうかは僕には分からない。
しかし、そこはどうでもいいところで、今回は対談相手の物理学者の方が非常に批判的思考を持ちながら対話を続けているところに価値があると思った。
とくに「感応技」(柳龍拳さんや西野皓三さんが披露されているもの)を「合気」としては否定されているのは、とても良いと思った。
僕は堀川派の技は好きなのだが、どうしても感応が強すぎるように見受けられる「受け」だけは気になって仕方がない。
「合気系」の技は思った以上の衝撃がくるので声が出るのも分かるが、「ちょっと大げさすぎるのでは?」と思うことも度々あり、そのあたりは「実力」からすこし差し引いてみるようにしている。
日本伝 岡本眞先生の技術論
ぼくがこれまでに技を掛けてもらった方で、もっとも強引さがなかったのが岡本先生だ。
気などの概念を用いずに解剖学的観点から説明しつくしてしまい、かつその理論通りに身体を操作されるのはスゴイと思う。
なんだかんだで合気と言っても、多少の「テコの原理」とか、雑めの「透明な力」でごまかされることが多い。
その意味で岡本先生の「合気」は、実際に受けたのはもう10年以上も前になるが、非常に印象に残っている。
今回「朝顔の手」のDVDを注文したので、到着を楽しみにしている。
ロシアン武術 システマ
先日、システマの初体験に行ってから「ストライク」に非常な興味が湧いてきた。
「ストライク」の「実用」と言ったって、実際に人を殴るわけでもあるまいが、整体や合気、はたまた日常の生活に活かせそうで、これは上達させたい技法だなと思った。
実際にシステマを体験してみて、合気道のときには分からない自身の緊張に気づくことができた。
パンチをよけず裁かず、そのままで受けるというのは日本の武術にはない発想だと思う。
猫の妙術 不動智神妙録 五輪書 無門関
いわゆる東洋思想関連。
「弓と禅」からの流れでいろいろ読んでみた。
やはり東洋には「無」の思想が強く流れている。
ここに個人的に惹かれるものがある。
猫の妙術における「道理」、沢庵に言わせれば「不動智」。
それを得るということ。
五輪書は、「姿勢」についての項目がもっとも参考になる。
無門関。読んでいるが難しすぎる…。公案は、アタマが狂いそうになるね。
考えるな、体にきけ!
日野晃さんの(おそらく)現時点での最新刊。
この本だったか、前著にて
「武道の極意は”相抜け”である」
と、武神館の初見先生を引き合いに説明されている。
「明鏡止水」の境地で、「相手と同時に動く」。
うむむ、この境地ももちろん武道には必要なんだろう。
孤塁の名人 深淵の色は
津本陽さんによる佐川先生の評伝。構成は読み難くて仕方がないが、内容は深い。
合気研究者なら必読の書と思う。
とくに透明な力だけでは読み切れない部分が見えてきたりして興味深い。
いろいろ調べていくと左門会と錬体会がトラブっているが、両方の視点から観るとまた違うものが見えてくる。
片方からだけ観ると、偏ってしまう。
「深淵の色は」の「易」の話は非常に興味深く、ぼくも少しだけ易の本を読み始めた。
また木村達雄先生が「合気修得への道」で書いた「合気は敵のスイッチを切る技術」という部分を訂正され、「調和」という概念にシフトされたことは非常に興味深い。
易によると、合気を「強くなろう」と思ってやってはいけないと。
ここにきて「陰陽」の思想が出てきたのは非常に面白いと思う。
大東流合気柔術 琢磨会ーその技法と合気之術
森恕さんの著書。
「抜く合気」について詳細な記述があり、非常に参考になった。
ただ「抜き方」に関しては文章では説明できぬということで
「こちらが力をふっと抜くと、相手も力が抜けてしまう」
というような解説に留まっている。
「合気ポイント」の説明に関しては保江さんの「骨と骨」理論に通ずるものがあるのではないかと感じた。
「手掌の一点」を攻める技法については、興味深いが手を取る技法以外では使えないので普遍性汎用性が低く、個人的にはあまり重視していない。
現在の個人的合気理論と実際。
以上、合気研究の先輩方の著作などを読んだ感想を備忘的にまとめた。
以下、現在のぼくに分かる範囲、出来る範囲での「合気」の考察と説明、今後の稽古の方向性などを記してみたいと思う。
この論では「合気」という単語を使うが、むろん合気が分かったわけでなく、ぼく個人の体験を説明するために単語をお借りしたと考えられたい。
個人的には「合気」とは佐川幸義先生が使った「相手の力を抜いてしまう技術」を指し、それが誰かに継承されたかどうかは分からない、という立場を取っている。
1:合気の基本
1-1 立ち方
ぼくが考える「合気の基本」というのは、まずは「立ち方」にある。
なるべく身体の緊張する部位が少なく、緊張する度合いが低く、必要最低限の力で立っている状態を理想とする。
きちんと立てると、不思議と思考が止まり「瞑想」に近い状態になってくる。
これで体幹部に「重力」が通ることになる。
1-2 肩の脱力
これが2つめの「合気の条件」になる。
「ちゃんと立つ」ことが出来ても、肩に力が入っているとそこで使うべき「重力」が途切れてしまう。
そこで「腕・肩の脱力」をすることでエネルギー(重力)を通す。
1-3 指先を活かす
手指の第一関節から先にだけを心持ち伸ばす。
これにより前腕のインナーマッスルが動き「重さ」が出てくる。
1-4 合気の基本 総論
基本のあり方として
体軸=実
肩=虚
指先=実
というサンドイッチ(もしくはオセロ構造)を作る。
それにより、相手の影響を受けづらく、相手に影響を与えやすい姿勢ができる。
ついリキんでしまい「体軸も肩も指先も実」という状態になりがちで、「脱力」を意識するとぜんぶ「虚」になってしまいがちだ。
しかし現在の僕の理論では「肩の力だけ抜く」というのが要諦になっている。
2:動く
2-1 歩き方
植芝盛平翁の「歩けば即、技になる」というのはどういう状態かを研究していくなかで、
「前述の立ち方のままで移動する」
という結論になった。
そのためには足に力を入れたり蹴って移動すると、つい重心が浮足だってしまう。
そこでなるべく「丹田を平行に移動させる」意識で歩く。
上下動、左右動を少なく。
足裏の重心位置については長年迷ったが、実際の使い勝手として「前足底」に重心を置き、踵を紙一枚分だけ浮かすのがベストだという暫定的結論になっている。
「薄氷踏むがごとし」「夜行丹田」などの足遣いはこれのことではないかという感触がある。
しかし武蔵のいう「踵を強く踏むべし」はいまだ解明にいたっていない。
3:技
3-1 触れれば即、技になる?
「触れれば即、技になる」と言えればいいのだが、現段階ではそうもいかない。
リラックスしたまま触れると、つい押し込まれてしまったりする。
そこで相手と触れるタイミングで、心なしか「張り」を出す。
すると相手に重みが伝わり「結び」が形成される。
この「張り」は太極拳における「ポン勁」にも通ずるものがあるのではないかと感じている。
3-2 オモテの呼吸力
インナーマッスルによって整えた骨格を保って動くと、思った以上に大きな力が出る。
これは合気道における「呼吸力」と言えるのではないかと感じている。
この「呼吸力」で入って、そこにテコなどが加わるとそれっぽい技が出来たりする。
これを「オモテの呼吸力」と呼んでいる。
そして個人的見解では、これが「透明な力」に値するものではないかと考えている。
3-3 ウラの呼吸力
しかし相手の骨格がしっかりしている場合、この「呼吸力」は効かずにぶつかってしまう。
そこで用いるのが「ウラの呼吸力」だ。
これは「張り」出していた力をコテから徐々にゆるめることで相手の力を入れにくくさせる技法だ。
これを「ウラの呼吸力」もしくは「力抜き」などと呼んでいる。
ポイントは接点の圧を変えずに体幹や肩甲骨周りの脱力をすることである。
こうすることで力のベクトルが不明になり持っている相手は混乱し崩れていくことが多い。
3-4 実ー虚ー実
しかし「虚」の状態になっても崩れない人も多い。
そこでもう一度「オモテの呼吸力」を使う。するとコロンと崩れることがある。
つまりまずは「オモテの呼吸力」で「結び」を作る。
その結びを保ったまま「ウラの呼吸力(力抜き)」によって力のベクトルをなくす。
そこで攻撃しにくくなり、混乱している相手にもう一度「オモテの呼吸力」を伝える。
実→虚→実
という流れの技法になる。
これは「透明な力」における
「合気で力を抜いたところに透明な力で投げる」
という記述と一致すると考えることができる。
4:場の空気とプラシーボ効果
ここまで一通り論を書いてみたが、まだまだ研究・試用段階であり失敗も多い。
達人のように見事に決まる例もあれば、「まったく効かない」ケースもある。
また「場の効用」もあり、「達人のような日」もあれば、「なんだか掛かりの悪い日」もある。
いずれにせよ、こちらのテンション、身体の調子、場の空気などが関連していると思われる。
そして「合気完結」で否定されていた「感応技」がたぶんに含まれているだろうと考える。
しかしこのあたりの「プラシーボ効果」的なものはゼロにすることはできないのだろう。
だからそれも効果のうちに入れつつ、なるべく排除しながら稽古していくしかないと考える。
佐川先生も
「技はバカにされたらかからない」から「恐れさせておくべきだ」と言っている。
5:今後の稽古の方向性
これは非常に悩ましく、ここをまとめるためにこれまで記述してきたと言っても過言ではない。
ただぼく自身が「武道」や「格闘技」の達人になれる可能性は極めて低いと考える。
やはり「武道の達人」になるには「ガチンコの打撃系」「格闘技」「ケンカ屋」などを出発点にしている必要があると考えている。
ではぼくのような軟弱者がなにを求めて合気を研究していくのか。
それはやはり禅的「忘我の境地」であり「平常心(びょうじょうしん)」なんだと思う。
そして、そこで起こる身体運動を見届けたい。
それが「達人風」だったら、それで充分たのしいと思う。
そのためには細かい技術も、陰陽の概念などもやるんだけど、あくまで補助的なものでやはり基本は
「立ち方」
なんだと思う。
「立ち方」「歩き方」を極めていき、そこから「触れ方」「技のかけ方」というふうに発展させていく。
そのなかで「脳波」や「魂」「心法」「相抜け」などが見えてきたらいい。
それから技の「陰陽」と「易」の関連ね。
じぶんの合気道の技が「天地自然の理」に適っているようでありたい。
ただ「自然体」の獲得のためには「自然体」というスローガンではなく
「不自然なまでの苦労・工夫」
が必要で、それを極めていった結果として最終的に
「自然体」
に到達するのだと思う。
その意味で「ひとり稽古」も続けるし、本も読むし、「小手先の技術」も研究していきたい。
結局その総体が、ぼく自身になっていんだと思う。
これからも未熟は承知で研究し、またその暫定的結論も発表していきたいと思う。
ご興味を持っていただける方は、こちらの動画も参考にされてください。