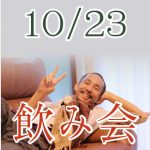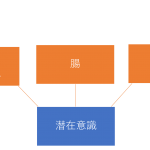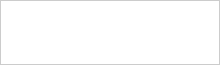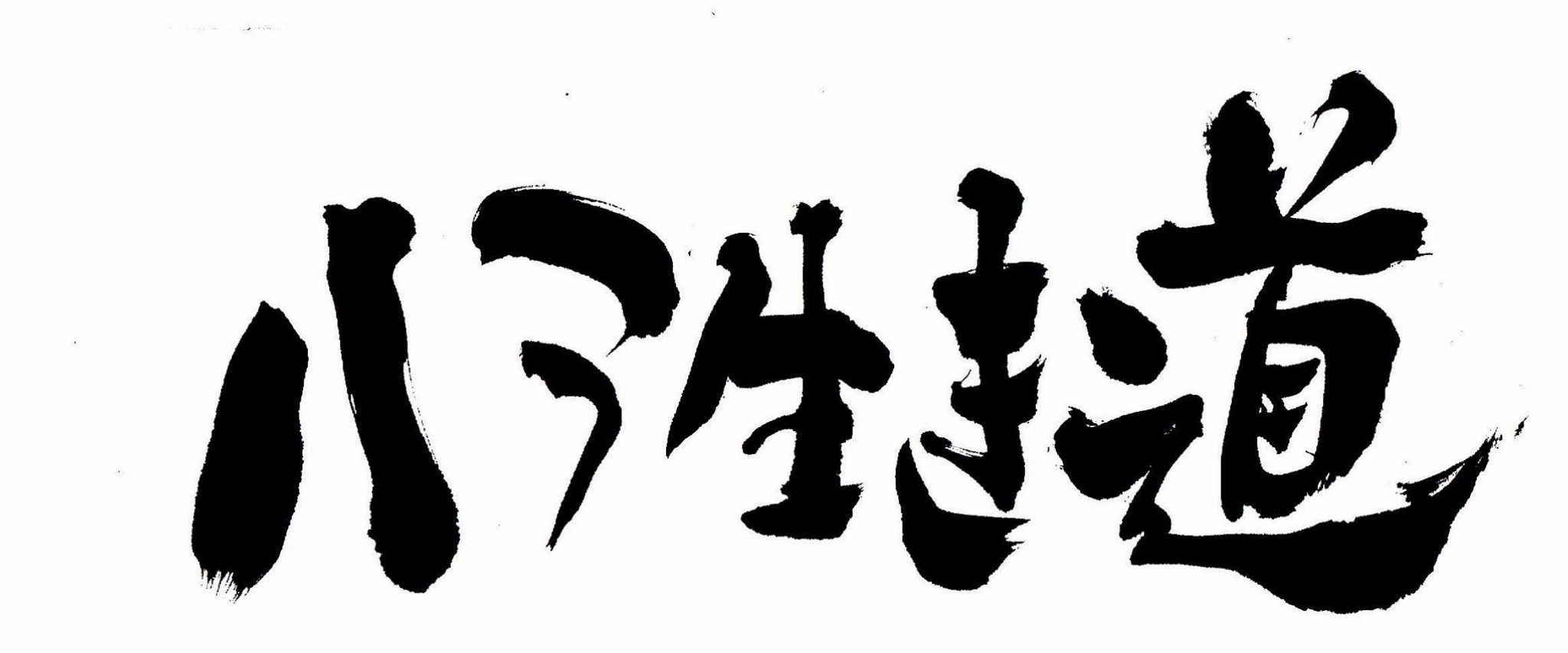すこしブームも廃れてきましたが、身体に興味がある人にとっては気になる存在なのが「古武術」。
というわけで、本日は「古武術」について筆を進めていきましょう。
目次
そもそも「古武術」って?
「古武術」という言葉が流行って久しいですが、実は「古武術」という言葉はもともとは存在しないのです。
武術に、「新しい」も「古い」もありません。
武術は武術です。「新武術」とか、「古武術」という分類はありません。
ではなぜ「古武術」という表現をするかというと、現在、学校で習う「柔道や剣道」のようにスポーツとして広まっている武道と区別するためだと思われます。
「武術・武道・格闘技・スポーツはどのように分類するか」というのは、非常に厄介な問題なので、ここでは取り扱わないことにします。
なので本来は難しい問題なのですが、誤解を恐れずに分かりやすく言えば、「古武術」というのは「近現代に入ってから安全面を考慮しつつスポーツとして発展してきた武道以外の、古来より伝わる武術」のことと考えていただければよいと思います。
なので、一般的に「剣術」と呼ばれるものは「古武術」として分類できます。
また「古武術」は「日本刀を使うことが前提の身体操作」と言うこともできます。
合気道は古武術なのか?
さてここで、ぼくの専門である合気道ですが、いったい合気道は古武術なのかというのは、これまた難しい質問です。

合気道は全世界で100万人の稽古者がいるとされており、非常に定義があいまいです。
スポーツ寄りの合気道、ダンスよりの合気道、プロレス寄りの合気道、学問寄りの合気道、格闘技寄りの合気道、気功寄りの合気道…
さまざまな先生が各自の研究をもとに研鑽されており、多種多様な合気道があります。
どれが正しくどれが間違っているということはありません。
それぞれに、それぞれの合気道があるのです。
そんななかで、ぼくとしては「マジック寄りの合気道」を研鑽しているのですが、そこに「古武術」のあり方や技術というものは非常に参考になりました。
こんな感じの合気道です↓
大雑把に言って、「古武術」の特徴というのは「柔よく剛を制す」、「やわらの発想」なのです。
筋力を強く太く大きくして強くなるという発想ではなく、身体を柔らかく遣い、「和していく」「包み込んでいく」「いなしていく」。
そういうことを極意として発展してきたのが古武術と言えるわけです。
その発想が新しいということで、温故知新、数年前に「古武術ブーム」がやってきたわけです。
ぼくも、「やわら」の面白さに心惹かれ、長年合気道をやってきました。
その意味で、今回の記事の文脈では「合気道」と「古武術」を、ほぼ同義で使用しています。
古武術や合気道は嘘?!総合格闘技で使えるか?やっぱり弱いのか?
さて、そんな古武術や合気道ですが、実際には「強い」のでしょうか?
「人を殺す術」として発展してきた古武術ですから、「実戦」で使えなければ意味がありませんね。
とはいえ、ほとんどの古武術や合気道の技は、残念ながら総合格闘技のリング上では通用しません。
つまり「使えなく」て「弱い」、ということになります。
古来より伝わる「やわらの術」が、なぜ「使えない」のか。
それには3つの理由があります。
1:練習量・稽古量が少なすぎるから
基本的に現代で武術をやっている人というのは、趣味でやっている方が99%だと思います。
となると、日中は仕事を持っていて終業後、もしくは休日に稽古をするということになります。
対して総合格闘技のプロは、1日に何時間も練習しています。
すると、どうしても「武術の達人」とあがめられ指一本で倒すパフォーマンスなどをしていても、総合格闘技のリングに上がってしまうと練習量の違いから格闘家に圧倒されてしまうということが起こります。
2:格闘技は、日本刀の使用を前提としていないから
たとえば極真空手にしてもガチンコで殴り合いますよね。
そのためにはどうしても鍛え上げられた筋骨が必要になってくるわけです。
しかし古武術や合気道では、基本的にその発想はありません。
なぜなら「ガチンコで殴り合う」ことよりも「刀で斬る」ということを前提に置いているからです。
「ガチンコで殴り合う」ことが前提の格闘技と「刀で斬る」ということが前提の古武術では、身体運用、身体操作の前提じたいが違ってしまいます。
その差がある状態で「リング」の上に上がれば古武術ではなく格闘技に軍配があがるのは当然と言えましょう。
3:格闘技にはルールがあるから
これは少し2とかぶりますが、基本的に古武術の基本として「卑怯」というのがあります。
「武士道」だったら卑怯は厭われるかもしれませんが、基本的に「殺傷術としての古武術」に「正々堂々」という考え方はありません。
ここでいう「卑怯」というのは、「なんでもあり」ということです。
かの宮本武蔵も、約束の時間に遅れてきたり、いろいろ心理作戦も織り交ぜながら佐々木小次郎に勝ったと言われていますが、それも「卑怯」の一種ですね。
「勝つため・負けないため」にはなんでもやる。それが古武術の考え方です。
しかしながら格闘技にはルールがあります。
ボクシングなら足技は禁止です。蹴りがあるキックボクシングなどでも金的(急所攻撃)は基本的に禁止ですね。
総合格闘技でも後頭部への打撃は禁止など、いろいろなルールがあります。
極真空手でも「顔面への打撃」は禁止、「なんでもあり」を標榜する武道でも、さすがにスーパーセーフ(顔面をガードする面)は使用します。
これは「ルールにのっとって正々堂々とやろうぜ」、ということになります。
となると「卑怯」がウリの古武術としてはスタートからして不利になってしまうのです。
以上のような理由から「古武術」を総合格闘技のリングで使うのは非常に困難と思われます。
古武術の人が総合格闘技のチャンピォンになっていないのは、そういう理由だとぼくは考えています。
これについては動画でも語ってみたので、よかったらご覧ください。
古武術や合気道で腕相撲が最強になる?
ということを考えると、古武術や合気道を極めたからと言って、腕相撲が最強になるということはないと思います。
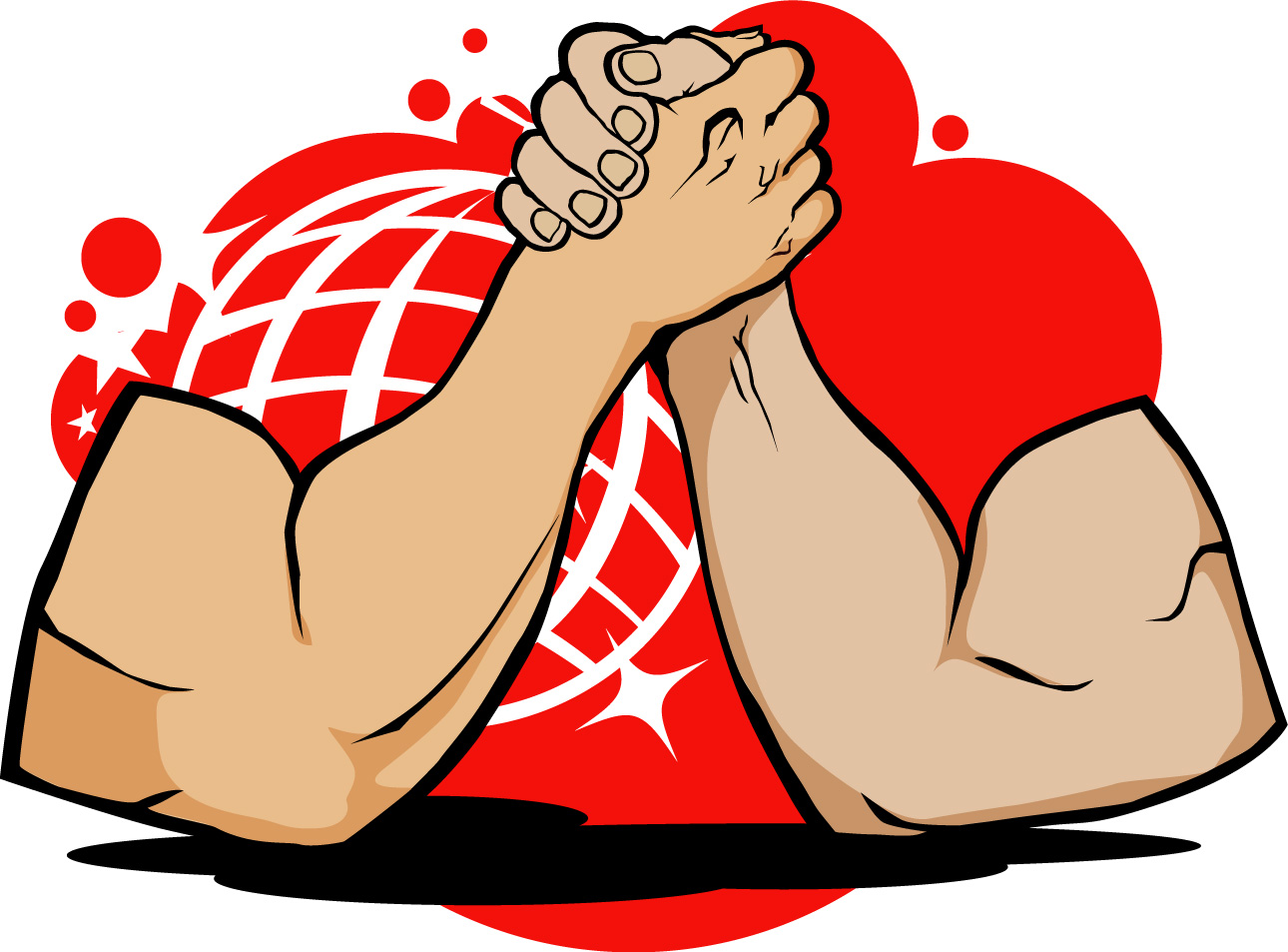
とくに古武術系では「空中腕相撲」と呼ばれる肘を固定しない状態でのパフォーマンスが見受けられますが、肘が固定されていないからこそ、全身の力を連動させたり、骨格をうまく利用して強い力を出せるのです。
上手な人だと「相手の力を出させない」という技術を使ったりもするでしょう。
しかし、実際のアームレスリングの試合のように「ルール」があり、がっちり肘を固定するとなると、それはやはり「アームレスラー」に軍配があがると思われます。
ちなみに個人的な研究の範囲でお話しすると、だいたい自分の通常の筋力の1.5倍~2倍くらいまででしたら「空中腕相撲」で勝つことが可能です。
しかし、それ以上となると全く歯が立たずに負けることがあります。
その意味でも「古武術万能説」のような中2病からは早いうちに脱却する必要があるでしょう。
ぼくの講座では、こういった「遊び」も行いますが、あくまで「パフォーマンス」であり、感覚が分かれば誰にでもできることです。
これは「達人技」ではなくて「達人ごっこ」なのです。
そのあたりを冷静に見ていく必要があります。
古武術や合気道は介護で使えるか?
「古武術介護」というのが一時期流行りましたが、実際に古武術は「介護で使える」のでしょうか?
これは結論から言うと「使える」と思います。

しかし一般に「古武術」の身体操作というのはカンタンではないので、どれだけ「カンタンにできる」という売り文句だとしても、なかなか身につかないのが現状ではないでしょうか。
ただ、調べてみるとちゃんと練習して腰痛にならなくなった人もいるようです。
そして、1回だけ研修に出て「使えない」と断定している人もいる。
それは「使えない」のではなく「興味がなく使う気がない」のです。
古武術の身体運用法というは、一言でいうと「エコな身体の使い方」です。
最大限に効率的に身体をつかっていく。
その意味では、介護どころか、ほぼ「何にでも使える」汎用性の高さがあります。
古武術や合気道に必要な姿勢や呼吸法とは?
では、そんな古武術や合気道の姿勢や呼吸法とは、どんなものでしょうか?

これは勿論ひとくちには言えませんが、大雑把に言って「ぶつからない」ことが基本になります。
「ぶつからない」とは「反作用を受けない力」です。
そしてそのためには、身体が「自然体」である必要があります。
「自然体」とは、骨格構造そのものが持つ強度(弾性・剛性)を最大限に活かせる状態です。
歩き方で言えば、大前提の基本は「地面を蹴らない」ことです。
地面を蹴る反動で進むのではなく、膝を抜くことで位置エネルギーを解放し、そのエネルギーで動くことです。
すると丹田が平行に移動することになりますが、そのときに最も効率的な歩き方になります。
また姿勢は「筋力でなく、バランスで立っていること」「インナーマッスルが活性化していること」「必要最小限の力で立つこと」「肩が脱力していること」「指先・手が活きていること」などが条件になってきます。
やはり、いずれも「刀」を前提とした身体運用法になります。
呼吸法に関しては、あまりに多くの種類があるため「古武術の呼吸法」という括り方はできません。
ただ一般には「腹式呼吸」「丹田呼吸」「密息」などが使われることが多いようです。
(また別記事で書きますね)
姿勢と呼吸法に関しては、無料の動画講座を作ってみたので、よろしければご覧ください。